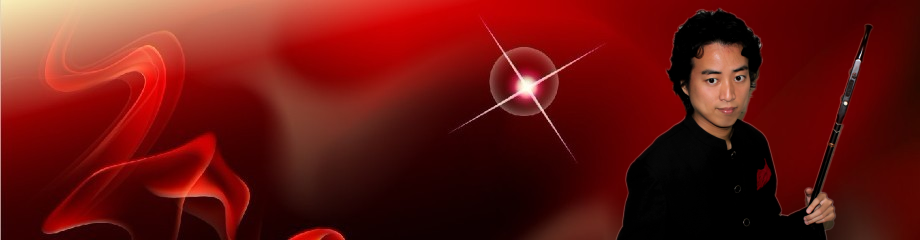二胡は胡琴に属する擦弦楽器です。
二胡の「胡」とは、モンゴルなど外の民族の総称でした。胡の楽器すべてを胡琴と言っていたのが、現在は弓弦楽器の総称として使われています。
二胡の由来についてはいろいろな説がありますが、唐の時代には、今の二胡とかなり近い形の「奚琴」と呼ばれる楽器が流行していたそうです。二本の弦の間から竹で弦をこすって音を出すというもので、この楽器の登場により、中国伝統楽器に四種の奏法「吹く、打つ、弾く、拉く」がそろったのでした。

宋の時代になり、稽(けい)琴と呼ばれる楽器へ進化、しばらくしてモンゴルから馬の尻尾を使った馬尾胡琴が現れ、その後の二胡、京胡、高胡などへの発展へ大きな影響を与えました。 その後、清の時代になり、洋琴(今の楊琴)、月琴、三弦、スオナー等多彩な中国楽器が生まれていきました。
(中国の人民音楽出版社の中国民間音楽概論より翻訳)